介護・医療関連ニュース
-
【どこまで分かる その検査】認知症リスク検査の最新事情 2種類の血液検査で将来の危険度判定
認知症の種類の中で、最も多く約60%を占める「アルツハイマー病」。脳にアミロイドβ(ベータ)という老廃物が20年ほどかけて徐々に蓄積し、神経細胞を障害して発症する。その発症リスクを調べる2種類の血液検査がある。各検査の特徴について、認知症に詳しい「銀座内科・神経内科クリニック」(東京)の霜田里絵院長が説明する。
「認知症を発症する前段階を『軽度認知障害(MCI)』といって、放置すると5~7年で約半数が認知症に進行するといわれます。最初に検査するなら、MCIのリスクを判定する『MCIスクリーニング検査』を受けるのがいいでしょう。採血は10cc程度です」
アルツハイマー病の原因となるアミロイドβは誰の脳にも発生するが、本来は排除する仕組みが備わっている。MCIスクリーニング検査は、その排除したり、毒性を弱めたりする仕組みにかかわる3つのタンパク質(アポA-I、TTR、C3)を調べる。
「この3つのタンパク質の血液濃度の変化や機能の低下を調べ、統計的手法で認知機能障害への程度を推定しているのです。開発メーカーの臨床研究の結果では、約8割の精度でリスクが判定できるとしています」
検査結果は4段階で示される。「A」は異常なし。「B」と「C」は、タンパク質の働きが弱まっているので要注意。「D」は専門医による精密検査や診断が勧められる。ただし、低栄養や重篤な肝障害、自己免疫疾患などがあると結果に影響が出る可能性があるという。
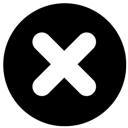
–– ADVERTISEMENT ––


